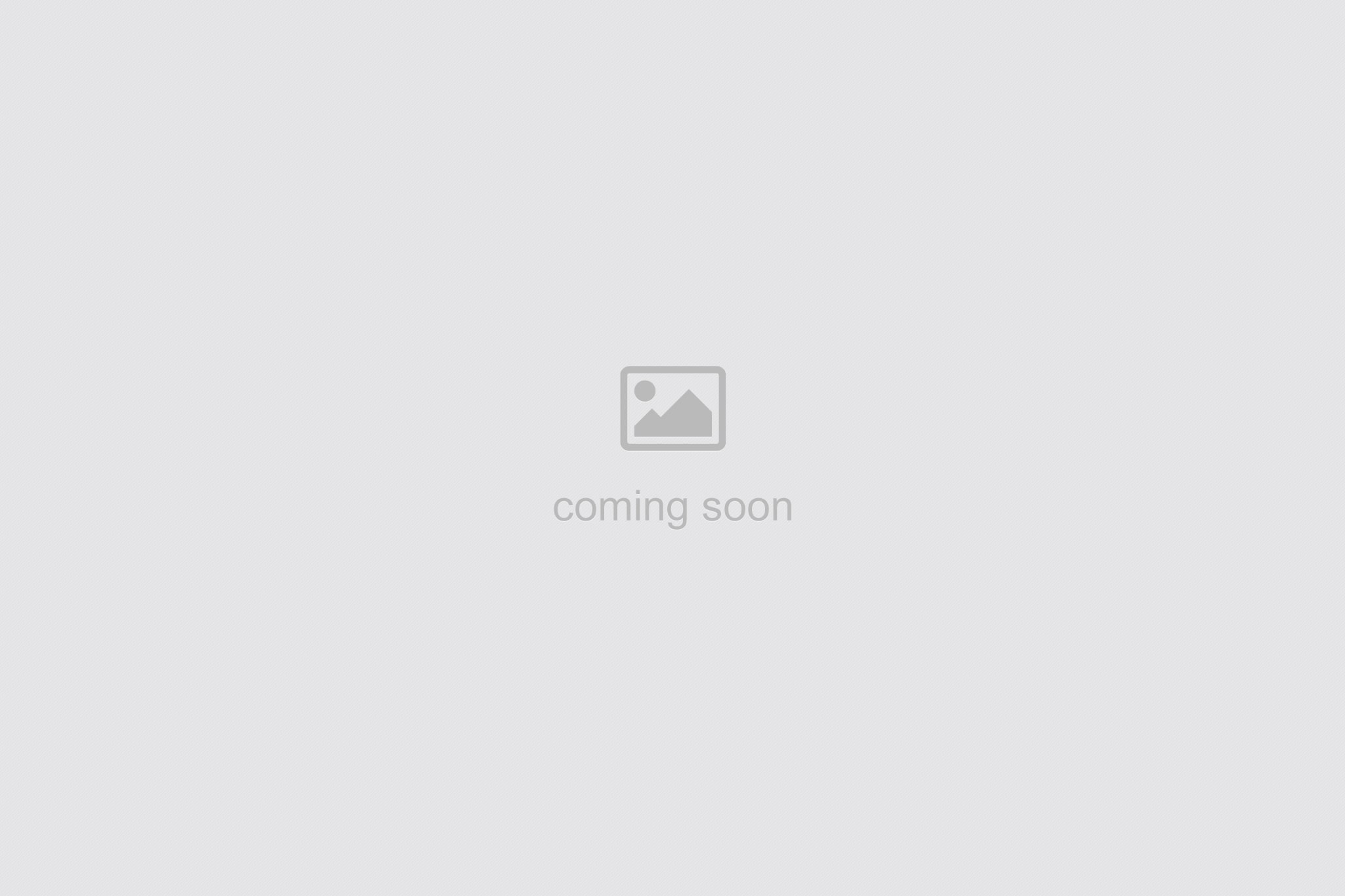新人社員と同行
「新入社員と同行」
新人さんと手入れと花植えに行ってきました。
今回は新人さんには花の仕入れ、花植えをお願いしました。
まぁ、花の数の多いこと。通りすがりのオバちゃんが見学するくらいの数です。
ダリアを中心にムニャムニャとムニャムニャ・・・。
すいません、マニアックな物が多く分かりませんでした。
勉強しなければ。
花を選ぶ際には花言葉も頭に置きながらだと楽しいですよね。
ダリアの使いやすい花言葉は感謝ですがあまり良くない花言葉は裏切り、移り気だそうです。
まぁ、悪い方で贈る人はいないと思いますが・・・。
花のチョイスも良かったと思いますがお客様にも大変、気に入っていただいたようです。
新人さんには熱い中、頑張ってもらい感謝、感謝でした。
社員旅行に行ってきました。
「社員旅行に行ってきました。」
先日、2年ぶりに3泊4日で台湾へ社員旅行に行ってきました。
台北を中心に故宮博物館、夜市、九分などメジャーな観光地も行きましたが勉強もかねて植物園にも行ってきました。
この台北植物園は約8ヘクタール、17エリアに分かれ2000種類が育つ広大な植物園でした。
やはり、日本と違って熱帯雨林の植物が多く見うけられましたが、なにしろ書かれた言葉が中国語と英語ですから多分、あれだよな・・・
といった感じでヤシやソテツの仲間を中心にハスやスイレンの池などを見てまわりました。
残念だったのは自分の好きな多肉植物が入っている温室が全部、クローズだったんです。「見たかった・・・。」
普段、あまり話すことのない人など社員みんなとの親睦も深まることもでき、とても有意義な時間が過ごせました。
しかし、海外に行くたびに言葉はもっと勉強しとけばよかったなとつくづく反省します。
下記の当社イベント情報でも社員旅行を紹介していますので覗いて見て下さい。
現場のつぶやき
掃除のはなし
ブロアーというマシンがある。
2サイクルエンジンを搭載し、ブンブン風を起こし落ち葉や埃を吹き飛ばす。
このマシン、1台で箒や熊手で行う作業の何十倍もの仕事をするし細かい埃も一瞬で吹き飛ばすから、仕上げには欠かせない優れもの。
たまにマンション・公園等で丁寧に落ち葉掃きをしている人たちを見るとつい「ブロアーを使ったら一吹きですよ」と教えたくなる。
ある朝現場に向かう途中、とある神社の前で管理者らしき人がブロアーを使って落ち葉清掃をしているところに出くわした。
ムムムムムム、なんだろうこの違和感は!
「落葉掃きは熊手と箒と塵取りでしょう!」と心が叫んでいた。
いつぞやとは正反対の、なんでしょうこのアンビバレントな心持ちは。
日本人には儀式だったり、修行だったり、ただ綺麗にするということ以上に深い意味が掃除には込められているんだと改めて気付かされた。
道具の使い方を教えることは出来ても、掃除を教えるのは難しいと思っている。
それは物事に対する姿勢の問題だから。
少しでも自分ごまかさない様に、1枚の葉っぱにも拘って掃除をしようと心がけている。
(S)
箒と熊手とてみ
ブロアー
現場のつぶやき 2017.10.27
手のはなし
ある先輩から手袋をしないで手入れをするようにしたほうが良いと聞き、素手で手入れをするようになって随分たつ。
「人間の指は最小13ナノメートルの凹凸パターンを区別できる。」とスウェーデンの科学者が明らかにしているそうだ。
手は本当に様々な情報を与えてくれる。
枝の弾力、葉の張り感、樹皮の凹凸、土の状態などなど。
ざらざら、ぬるぬる、ざくざく、皮膚感覚は人に伝えることは難しい。
それは個人的なものだから。そしてそれが職人としての大きな財産になる。
もちろん、バラのように棘のある植物の手入れや、伐採等、怪我をする可能性のある場合は別だけれど。
でも今は怪我はあまりしない、ちょっとした切り傷や、棘がたまに刺さるぐらい。
手袋をしていてもしなくてあまり変らない気がする。
持ち方、触り方なんかをことある毎に学習していったのだと思う。
少しずつ自分の体に色々な耐性が付いていったのだと思う。
土には雑菌がいたり、樹液が皮膚炎を起こさせたりすることもあるので、
一般の方が庭の手入れをする場合には、やはり手袋を着用しての作業をお勧めする。
皮膚の間に入り込んだ汚れは頑固で、その手で一年生の娘に触れようとすると「きゃっきゃ」言って逃げる。
いつか、働き者の綺麗な手、といってもらえる日が来るといいなと思う。
(S)

造園技能検定試験に挑戦!!


造園技能検定試験を受けて来ました。
試験内容は、垣根を作る実技試験、知識を問われる学科試験、樹種を見分ける要素試験の3項目。
平均合格率は1級で3割、2級で4割ほどです。
3ヶ月ほど前から休みの土日を使い練習を重ねて来ました。
試験当日は生憎の雨、地面が田んぼのようになっていました。
場所によっては膝ぐらいまで埋まってしまう状況です。
いかに敷地を汚さずに、時間内に作業を完了するかが大きなポイントとなりました。
どの受験者も足をとられ思うように施工できない中、それでも何とかほとんどの人がそれなりに形を作り上げ
さすが職人集団と思わされました。
みんな頭のてっぺんから足の先までずぶぬれで、泥だらけで大変な状況でした。
試験終了後は、頑張ってくれた道具たちの泥を水で洗い流し、感謝を込めてピカピカにしました。
試験を受けるにあたり沢山の先輩が色々な角度からアドバイスをしてくれ、細かなコツを教えてくれました。
そんな優しさにも触れることが出来、とても意味のある試験になったと感じました。
この経験を今度はお客様の現場で活かしていきたいと思います。
やれることは全てやりきったので、9月末発表される結果を楽しみに待ちたいと思います。
現場のつぶやき~
『バラの玉』
先日、会社のバラの花柄取りをしているとちょっと面白い物を発見しました。
葉っぱにピンクの丸い球体が!
さわると堅くて木の実みたい。
バラの色に似てとても綺麗。
バラの実!?種!?なんだなんだ、これは一体!?
調べてみると『バラハタマバチ』のという蜂が作る虫こぶと判明しました。
この虫こぶは正式にはバラハタマフシというそうです。
バラハタマバチはバラの葉に卵を産み虫こぶを作ります。
そしてこのこぶの中で幼虫はこぶを食べながら生長するのだそうです。
割ってみると中には、本当に真っ白な幼虫が入っていました。
しかし本当に上手に綺麗に球体を作っており、関心してしまいました。
しかもバラの葉の組織を利用するとは!
ちょっと関心を持って眺めてみると、自然界は本当に面白く魅力的な世界が広がっています。
人間には計り知れない知恵をもって、一生懸命生命をつないでいる、感動ですね。
(S)
現場のつぶやき~

青色:オオイヌノフグリ
紫色:カラスノエンドウ
白色:クサイチゴ

蜜を吸うアリ

群生するナガミヒナゲシ

ハルノノゲシに集まるアブ
「雑草という草はないんですよ。」
「雑草という草はないんですよ。どの草にも名前はあるんです。」
昭和天皇のお言葉です。
最近”雑草”と呼ばれる草花達を観察したり、調べたりしています。
個々に見ると本当に美しく、心惹かれるものがあります。
名前や、勢力拡大のための戦略なども本当に面白い。
ナガミヒナゲシが群生して咲くのは、他の植物の芽生えを阻害するアレロパシー物質を根からだしているから。
カラスノエンドウにアリがいるのは花外蜜腺という器官から蜜を出すから。
花や虫たちはただ何となくそこにいるのではなく、いるべくしてそこにいるんだ、と分かるとじわじわ感動が!
もし雑草が一本も無くなってしまったら、里山の風景はなんて寂しいものになってしまうだろう。
子供たちと散歩に出かけ、ちょっと自慢げにこんな話をするのを楽しみにする父なのでした。
(S)
現場のつぶやき~
地上10m付近での確認作業
実生のモチノキ
「樹上の神秘」
先日ご依頼のあったお寺に伺い、樹高20m程の大イチョウの枝下しを行いました。
先輩のNさんが高所作業車を使い剪定し、私は下で落下枝の処理と、通行人の誘導を行います。
通常落葉樹のイチョウはこの時期には全ての葉を落としているのですが、Nさんの剪定を観察していると、ふっと緑の葉のあることに気が付きました。
ムムムムム、なんだなんだなんだ!
好奇心に火が付いた私は休憩時間に確認することに。
2連梯子を使い上ってみるとそこは洞になっていて、見覚えのある植物が生えています。
こんなところにモチノキが!
周囲を見回すと他の洞にもイボタノキやムラサキシキブが生えています。
きっと鳥たちが種を運んだのでしょう。古木の洞は根を張るのに丁度いい環境だったのでしょう。
多くの植物がこのイチョウと共生していたのです。
鳥、虫、苔、植物、菌類そして人。
いったいこの老木をどれだけの生命が拠り所としているのだろう。
自然の力強さと寛容と不思議さに心を打たれました。
このような出会いや気づきは私に日々多くのパワーを与えてくれます。
そして自分の小ささにも気づかせてくれます。
なんだかとても有難い気がします。
(s)

「樹上の風景」
この仕事をしていると、はっと息を飲む風景に出会うことがあります。
植木屋にしか出会えない、筆舌に尽くしがたい景色。
そんな特別な風景を、ご紹介してみたいと思います。
左の写真。
優しいグリーンの絨毯の奥にはクスやケヤキの深い緑が立ち並び、透明感のある空のブルーに浮かぶ白い雲。その間から射す淡い陽光。
これ、どこから見たところだと思いますか。
実は、弊社が管理させて頂いている小田原にある某公園の藤棚の上から見たところなのです。
この下には観光で訪れた人達が歩いています。
余計なものが一切目に入らない風景は自然の美しさそのものでした。
緑は本当に人の心を豊かにしてくれます。
日本でもこんな風景が見られるのかと、休憩時間に脚立をかけ見とれていると、この仕事をしていて良かったとつくづく思わされます。
”緑は人を潤す”そんな心奪われる場面に出会えることを楽しみに、日々仕事に勤しむのも植木屋ならではのことなのではないでしょうか。 (S)